デッドビート – 第9章.2

ディミタールとスリムは、現在共有しているテーブルの反対側の端、シート2とシート8に座っていた。他のプレイヤーも同席していたが、2人の男が独自のゲームをしているような雰囲気が次第に高まっていた。フェルトからの更新を執筆する記者たちにとって、この物語は焦点を当てやすいものだった。ファンたちはオンラインで反応し、ソーシャルメディアで繰り広げられるエキサイティングなハンドを見守り、アクションについてコメントしていた。
特にあるハンドでは、ディミタールが大きな打撃を受けた。彼のリードはスリムに奪われたが、それはチップの面でのみだった。ボードは、ディミタールが常に手元に置いている水のボトルよりも濡れていた。彼は水分補給を心がけ、頭上のエアコンと増大する疲労感に対抗していた。1日が終わる頃には6人のプレイヤーが残り、12人が残っていた時、ディミタールはミドルセットをフロップした。彼のポケットエイトがT-8-7のフロップで3枚目のスノーマンを見つけたのだ。3枚ともハートで、もし9が現れればストレートの可能性があった。そして、ターンでダイヤの9が落ちた時、それが現実となった。
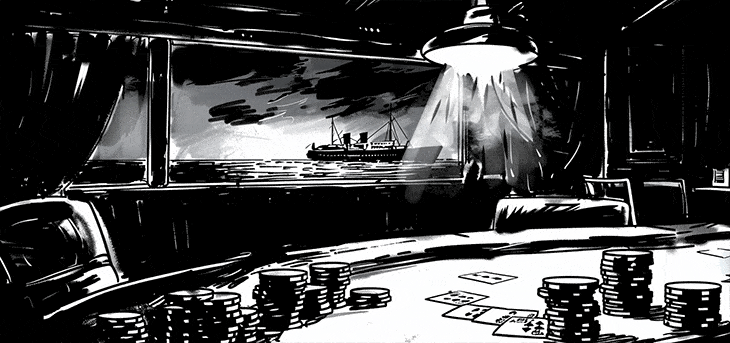
スリムはベットリードを取り、ディミタールはレイズして、年上の男がストレートかフラッシュを完成させたかどうかを確かめようとした。スリムはリレイズし、若い対戦相手をじっと見つめた。
「フォールドすれば、俺がチップリーダーだ。それで満足だよ。」スリムは微笑んだ。
「俺もだ。リードは重要だが、チップを持つことも同じくらい重要だ。」ディミタールはそう言いながら、カードをテーブルに表向きに投げ捨ててフォールドした。それは不器用な動きで、エイトの1枚が空中でひっくり返り、もう1枚から少し離れた場所に裏向きで着地した。ディーラーは両方のカードを一瞬だけ表向きにし、スリムは微笑んだ。彼は自分のカードを裏向きのままマックに滑り込ませた。
次の休憩時には、残り9人となり、2人の男はバーで飲み物を交わした。
「それで、持ってたのか?」
「もちろんだ。9も持ってたよ。君が手にジャックを持っていないと推測したんだ。」
「どうして分かったんだ?」ディミタールが尋ねた。
「君のベットサイズさ。ジャックがなければ、少し控えめにするだろう。8アウトよりも7アウトを少しだけ怖がるからね。」
「俺は常に学んでいる。」
「君はとても上手にプレイしているし、良いフォールドをした。でも、自分の実力をテーブルに見せるな。若い頃、俺も同じ間違いをたくさんした。自分がどれだけポーカーが上手いかを世界中に知らしめたかったんだ。」
「それの何が悪いんだ?強さを示し、恐怖を植え付ける。」
「君のホームゲームや地元のカジノではそれでいいかもしれない。でも、一般の人々が見られるゲームでは違う。それはバリューベットを失う可能性があるし、評判を与えることになる。君が他のプレイヤーに与える情報は、彼らが君のレンジを確立する助けになる。ベット、レイズ、コール、すべての動きにおいてね。」
「君に見せれば、君がブラフかストレートかを見せてくれると思ったんだ。」
「もし俺がそれをしたら、誰のためになる?君のためか?君のことは好きだが、君に少し疑念を持たせたい。俺がスーパーなブラフをしたと思わせるかもしれない。実際にはしていないし、君がフォールドしたのは正解だった。でも、もしそれを他の人に見せたら、俺は自分を弱めるだけでなく、ハンドの真実をさらけ出すことになる。それは彼らを助けるだけだ。」
「そんな風には考えたことがなかった。」
「分かってる。君は素晴らしいプレイヤーだ、ディミタール。でも君は疲れている。遅い時間に大きなミスをするな。それを後悔することになる。」
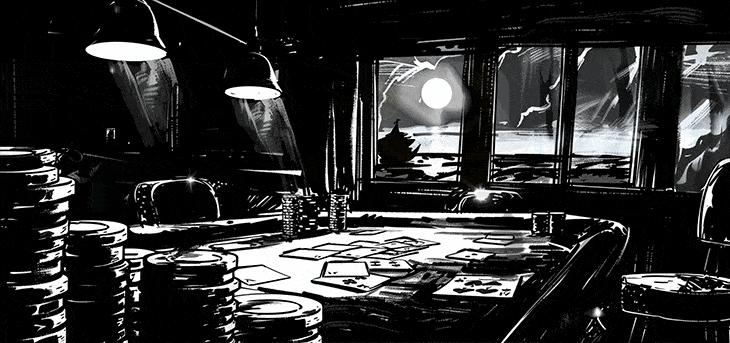
「君が他の人のためにこの集中力でプレイしているなんて信じられない。」
「どういう意味だ?」スリムが言った。頭上では、アクションが再開されることを示すライトが点滅していた。その夜の最後の2レベルは、おそらく6人ハンドのファイナルテーブルをもたらすだろう。
「君のチャリティーのことだ。君は他の人のためにプレイしている。お金は君には入らない。でも、それが君にとってとても重要なんだ。一つ一つのハンドがね。それが分かる。」
「他の人のためにプレイしているからこそ、俺にとってはもっと重要なんだ。彼らは俺よりもお金を必要としているし、俺はポーカーをプレイすることで自分が持っている以上のお金を稼ぐことができる。」
「それを聞くと、まるで単純な方程式のようだ。」
2人の男はバースツールから立ち上がり、他のプレイヤーを避けながらテーブルに戻った。
*
その日はヨーロッパを駆け抜ける景色を眺めながら過ぎていった。正午過ぎには食堂車で昼食をとり、エレナはサーロインステーキと野菜を選び、ドレスの下にある傷跡を感じていた。服の下に隠れた2インチの盛り上がった線は、通り過ぎる誰にも見えないが、何が起こったのかを永遠に思い出させるものだった。
「少なくとも今は食べているね。」セルフは微笑んだ。「君は強くなっている、エレナ。」
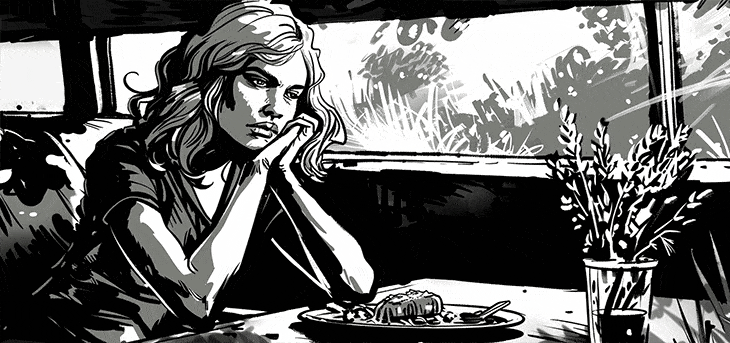
食事の後、彼らは自分たちの車両に戻り、残りののんびりとした午後を過ごした。彼らは早めに自分たちのベッドに入り、空がまだ明るいうちに休んだ。雲は薄いオレンジ色で、ゆっくりとした動きで黄昏の灰色に飲み込まれていった。昨夜のことを考えるとセルフに飛び込むのは狂気の沙汰だったので、彼女はそれを抑えた。彼女は今、もっと現実的に考えていた。彼が何を信じるか、その話がどれだけ信頼できるか。
夜が更けると、彼はうたた寝から目を覚まし、少し話した。「エレナ、君に謝りたい。」
彼女は自分のベッドの上のライトをつけた。彼らは1メートルしか離れておらず、彼は自分のライトをつけなかった。それでも十分に見えた。寝台列車は西ヨーロッパの田園地帯をゴトゴトと進んでいた。
「分かってるわ、ピーター。それがあなたが正しいことをするべき理由よ。」
「君が俺の名前を憎しみなしで言ったのは初めてだ。」
「あなたを憎んでいるわけじゃない。同情しているの。それに、あなたが経験したことの一部はディミタールのせいだけど、彼があなたの妻と寝た時、あなたに何が起こるかなんて考えていなかった。彼女が彼と一緒に決断したことだったのよ。」
一瞬、エレナはセルフの目の色が端に押しやられ、黒い瞳孔が広がるのを見た。その暗さは、彼女がベッドの横のランプの光と同じくらいはっきりと見えるものだった。ただし、それは正反対だった。それはまるでブラックホールのように部屋の生命を吸い取るように見えた。
「彼らの間に何があったのか、私たちには分からない。ディミタールが今何をしているのか、誰と一緒にいるのかも分からない。」
「どうしてそんなことを言うんだ、俺を傷つけるためか?」
「昨夜、私たちが一緒に過ごしたことを彼が知ったら、彼は傷つくと思う?」彼が尋ねた。
エレナは答えなかった。やがてセルフは再び眠りについた。彼女はベッドのカバーの下を探り、次にベースシートの下を探った。そして、マットレス自体の下に指を押し込んだ。セルフがベッドのスプリングの音を聞かないように、ミリ単位で慎重に動かした。ついに、永遠にも思える時間の後、エレナの指先がステーキナイフの先端に触れた。彼女は静かに手を引き、ランプの光の中でそれを見つめた。そのランプはつけたままにしておくつもりだった。
一滴の血が浮かび上がった。彼女はそれをすぐに吸い取った。
著者について: ポール・シートンは10年以上にわたりポーカーについて執筆しており、ダニエル・ネグラヌ、ジョニー・チャン、フィル・ヘルミュースなど、史上最高のプレイヤーたちへのインタビューを行ってきました。これまでに、ラスベガスで開催されるワールドシリーズオブポーカーやヨーロピアンポーカーツアーなどのトーナメントからライブレポートを行ってきました。また、他のポーカーブランドでメディア責任者を務めたほか、BLUFFマガジンでは編集長を務めました。
この作品はフィクションです。実在の人物、出来事、または団体との類似は純粋に偶然のものです。





